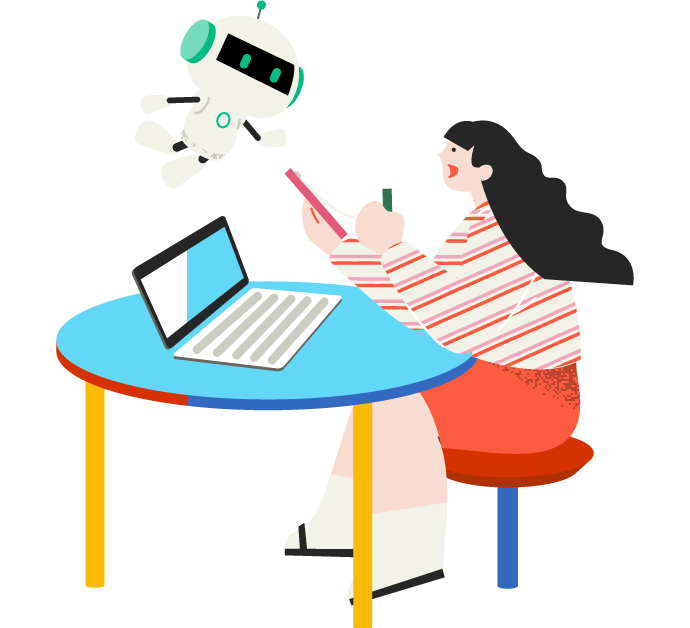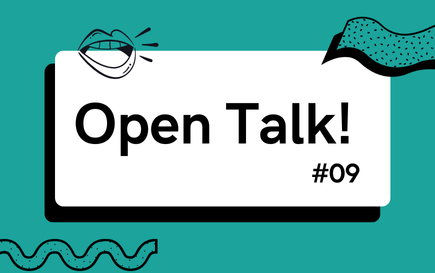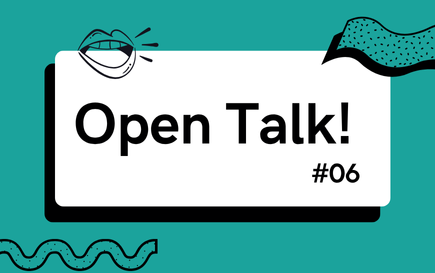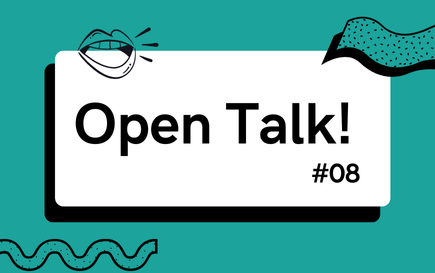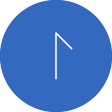コンテンツマーケティング・アカデミーのスタッフ3名が、マーケティングやコンテンツにまつわるテーマについて、気ままにフリートークします。
今回は、AIが直接データベースにアクセスする「MCP」技術について。これまでのGoogle検索に代わる新しい情報取得の形が、私たちの働き方をどう変えるのでしょうか?
参加者プロフィール
村上健太
コンテンツマーケティングアカデミー、チーフストラテジスト。企業のコンテンツ戦略立案に携わり、最新のAI技術動向をウォッチしている。
髙山はるみ
コンテンツマーケティング、リサーチャー。長年企業ウェブサイトの制作に携わり、検索技術の変化を現場で実感している。
今井静香
コンテンツマーケティング、リサーチャー。生成AIの活用に関心が高く、新しい情報検索の可能性を探求中。
#1:MCPって何?これまでの検索と何が違うの?
今井:最近「MCP」っていう技術が話題になってますけど、これって何ですか?
村上:MCPは「Model Context Protocol」の略で、生成AIが外部のデータベースやツール、サービスと効率的に接続するための技術です。生成AIと外部のシステムがやりとりするための「便利な共通言語」みたいなイメージですね。
例えば、近所の●●スーパーが在庫情報をMCP対応で公開していれば、「今日●●スーパーの特売中の商品は?」とAIに聞くだけで、AIがリアルタイムの在庫データにアクセスし、最新情報を教えてくれます。
お客さんはこれまでみたいにお店のホームページを見に行く必要がないですし、お店側も独自のAPI連携を開発する必要もありません。様々なサービスやデータとAIを簡単に連携できるようになるんですね。
髙山:つまり、ホームページに載ってない情報まで検索できるってことですか?
村上:まさにそう!従来のGoogle検索は「ホームページに書いてある情報」しか見つけられませんでした。でもMCPならページに掲載されていない在庫状況や価格などの「リアルタイムの情報」まで取得できたりします。さらにECシステムにMCP経由で接続すれば、AIチャットから商品の購入などのアクションも指示できるようになるんですね。
このように、普段使っているAIチャットを通じて、さまざまな外部データの取得や操作が一元的に行えるのがMCPの大きな特徴です。
今井:すごいですね。でも、これってGoogleにとっては脅威なんじゃないですか?
村上:実際、「もうGoogleいらないんじゃない?」って声も出始めました。MCPの普及はまだまだこれからですが、現時点でも既に「Google検索よりも、Perplexityパープレキシティ:AI検索サービスの一つ)のような検索に強い生成AIサービスのほうが便利だよ」という声をよく聞くようになりました。
AIチャットなら細かく単語を区切って検索する必要もないし、今のところ広告も少ない。「週末に家族で行けるお得なレストラン教えて」って普通に話しかければ、すぐに答えが返ってくるわけですから。さらに今後MCPを活用した情報取得やサービスが広がれば、ますます便利になりますね。
髙山:なるほど。でも、すべての企業やお店がMCPに対応してくれるんでしょうか?
村上:そこが課題ですね。技術的には素晴らしくても、企業側がデータを公開するかどうかは別問題。コストもかかるし、競合に情報を知られたくない場合もある。普及には時間がかかるかもしれませんね。

引用:Firmbee.com
#2:GoogleのAIモード参戦!検索戦争の行方は?
村上:面白いことに、Googleもこの動きに危機感を抱いてるみたいで、つい最近「AIモード」を追加すると発表しました。
今井:えっ、Googleが?どんな機能なんですか?
村上:これまでの検索結果ページの「すべて」って書いてあるタブの隣に、「AIモード」っていうタブが追加される予定です。基本的には前出のPerplexityのようなイメージですね。
髙山:どういう体験になるんでしょう?
村上:普通の会話みたいに質問できて、そのまま回答が表示されます。合わせて「この情報はこのサイトから取得しました」って参照元も表示してくれる。これまでの検索結果ページとは全然違う体験ができるようになりそうです。
今井:でも、それって広告はどうなるんですか?Googleの収益源ですよね。
村上:そこが微妙なところで(笑)。GoogleだからAIモードでも何かしら広告を入れてくる可能性は高いです。ただ、チャット形式での広告表示って従来と全然違うから、どんな見せ方になるかは未知数ですね。
髙山:検索業界全体が大きく変わろうとしてる感じですね。
村上:そうなんです。こうした一連の変化の中で「GEO(生成エンジン最適化)」や「LLMO(大規模言語モデル最適化)」っていう新しい言葉も出てきています。これまでの「SEO(検索エンジン最適化)」に代わって、「AI検索向けの最適化」が重要になってくる。
これまでのSEOは「Googleの検索アルゴリズムにどう対応するか」ということでしたが、これからは、AIがウェブ上の情報を学習・参照する際の「AIに好まれるコンテンツ作り」が大切になるってことです。

引用:Markus Winkler
#3:企業はどう対応すればいい?新時代のマーケティング
髙山:こういう変化って、企業のマーケティング活動にはどんな影響があるんでしょうか?
村上:まず、これまでの検索対策の考え方を見直す必要がありますね。Googleの検索結果で上位に出ることを狙うだけじゃなくて、AI検索で適切に情報を提供できるような情報発信が重要になってくる。そうした認識がマーケティングチームの中でしっかり広がっている必要があります。
今井:なるほど。具体的にはどんな準備が必要ですか?
村上:まず、自社の情報をAIが参照しやすい形できちんと整理することです。商品情報、商品説明、店舗情報などの公式情報を、明確で網羅的なコンテンツにしていく必要があります。さらにそうしたコンテンツに対して、AIが内容を正確に理解できるよう、構造化データや明確なメタデータを付与したほうがよいという声もあります。「AIの回答に自社の情報がどれだけ採用されるか」が新たなカギになるというわけですね。
髙山:制作現場としても、新しいスキルが必要になりそうですね。
村上:そうですね。従来のキーワード重視の記事作りから、AIが文脈や意図を理解してもらえるようなコンテンツ設計にシフトしていく必要があるのかもしれませんね。
今井:AIとの相性を考えたコンテンツ作りって、どんな点に注意すべきでしょうか?
村上:重要なのは「AIが理解しやすい論理的な構造」を意識することです。結論を明確にして、根拠を整理し、 関連情報のつながりを明示する。曖昧な表現より、具体的で測定可能な情報を優先する。AIは論理的で明確な情報構造や信頼性の高いデータを重視するため、こうした工夫がなされたコンテンツがAIに選ばれやすくなりますね。
髙山:これまで以上にコンテンツの質が問われる時代になりそうですね。
今井:でも、そう考えると良いコンテンツを作ってる企業にとってはチャンスでもありますよね。
村上:まさにその通り!表面的なSEOテクニックより、深くてためになる本当にユーザーの役に立つ情報を発信しているコンテンツが評価される時代になるといいですね。

引用:Scott Graham
#4:私たちの働き方・情報収集はどう変わる?
今井:この技術革新で、私たちの日常的な情報収集って、どう変化すると思いますか?
村上:最も大きいのは「情報収集の効率化」ですね。これまでは複数のサイトを見比べて情報を集める必要がありましたが、AIが最適な情報を整理して提示してくれるようになる。例えば「今週末の家族旅行先を探してる」って伝えれば、天気予報、宿泊施設の空き、現地イベント、交通状況まで一度に教えてくれる可能性があります。そのままAIとのチャットの中で、ホテルの予約やレジャー施設のチケット購入もできてしまうでしょうね。
髙山:すごく便利になりそうですけど、情報の信頼性はどうでしょう?
村上:これは重要な課題です。AIが提示する情報の根拠やソースを確認する習慣が、これまで以上に大切になってきます。便利になる一方で、情報の真偽を見極める能力も求められる。「AIが言ってるから正しい」じゃなくて、「なぜそう判断したのか」を理解する姿勢が必要ですね。
今井:私たちコンテンツ制作者としては、どんなスキルを身につけるべきでしょうか?
村上:AIとの協働を前提としたコンテンツ作りが重要になります。AIが得意な情報整理や構造化はAIに任せて、人間は創造性や独自の視点、感情に訴える表現に特化していく。また、AIが理解しやすい形で情報を整理して伝える技術も必要です。
髙山:技術の進歩に合わせて、私たちも学び続ける必要がありますね。
今井:でも、変化が早すぎて追いつくのが大変そうです(笑)。
村上:そうですよね。そこで大切なのは、技術に振り回されないことです。MCPもAI検索も、あくまで手段。重要なのは、これらの技術を使って何を実現したいか、どんな価値を提供したいかっていう目的を明確にすること。技術ありきじゃなくて、ユーザーのニーズや課題解決を起点に考えていく姿勢が大切だと思います。
髙山:確かに。技術は進歩しても、人の役に立ちたいっていう気持ちは変わらないですもんね。
今井:新しい技術を恐れずに、うまく活用していきたいですね。
まとめ
今回は、MCPとAI検索の進化について話し合いました。従来のGoogle検索からAIチャット検索への移行、企業マーケティングにおけるGEOの重要性など、大きな変化の時代を迎えています。大切なのは、技術に振り回されないこと。MCPもAI検索も、あくまで私たちの生活を豊かにするための手段です。技術ありきで考えるのではなく、ユーザーのニーズや課題解決を起点に、「人の役に立ちたい」という気持ちを大切にしながら、新しい技術をうまく活用していく姿勢で新時代を迎えることが重要なのです。
執筆・編集:Content Marketing Academy