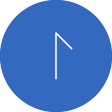コンテンツマーケティング・アカデミーのスタッフ3名が、マーケティングやコンテンツにまつわるテーマについて、気ままにフリートークします。
今回は、芥川賞作家の九段理江さんが生成AIと共に小説を執筆した話題から、生成AIとの新しい向き合い方について語り合いました。プロンプト集に頼るだけでは限界がある理由とは?
参加者プロフィール
村上健太
コンテンツマーケティングアカデミー、チーフストラテジスト。企業のコンテンツ戦略立案に携わり、最新のAI技術動向をウォッチしている。
髙山はるみ
コンテンツマーケティング、リサーチャー。長年企業ウェブサイトの制作に携わり、検索技術の変化を現場で実感している。
今井静香
コンテンツマーケティング、リサーチャー。生成AIの活用に関心が高く、新しい情報検索の可能性を探求中。
#1:芥川賞作家が示した「生成AI活用」の衝撃
村上: 最近話題になった芥川賞作家の九段理江さんのAI小説、皆さんはどう感じました?
今井: 正直、「どんなすごいプロンプトを使ったんだろう」って期待してたんです。でも実際に公開された内容を見て、びっくりしました。
高山: 私も!てっきりコピペで使えそうな技術的なプロンプトが出てくると思ってたのに、全然違いましたね。
村上: そうなんですよね。九段さんのやり取りって、最初は「初めまして、私を知っていますか?」という挨拶から始まって、DAY3には「久しぶり、クリスマスは何してた?」って、まるで友達と話してるみたいでした。
今井: それって、一般的なプロンプト集とは全く違うアプローチですよね。
村上: まさにそこがポイントです。効率的に生成AIを使おうとして「生成AIを効率的に使うためのコマンドを覚える」という発想になりがちですよね。でも、九段さんは完全に「対話相手」として扱っているのが印象的ですね。
高山: 確かに、私たちがWebサイト制作で生成AIを使う時も、つい最初から「○○を作成してください」という指示的な使い方になりがちです。でも実際に生成AIと対話するように使うと、どんなメリットがあるんでしょう?
村上: 例えば、ブログ記事を作る場合を考えてみましょう。従来の方法だと例えば「生成AI時代のマーケティングトレンドに関する4000文字の記事を書いてください」といきなり依頼しますよね。でも対話形式なら、まず「最近のマーケティングトレンドについて、どう思いますか?」みたいなことから始めて、段階的に内容を深めていくイメージですね。確かに無駄なインプットになって時間はかかるかもしれませんが、私たち人間の側がじっくり考えを深めながら進められる良さはありますよね。さらに、作家のように言葉や概念に長けた方が扱うと、十分オリジナリティがある優れたアウトプットが産まれやすいのだと思います。
生成AIを使うというと、どうしても業務効率化が目的となるので、無駄を省いて最短距離で…となるのですが、それとは違ったアプローチですね。
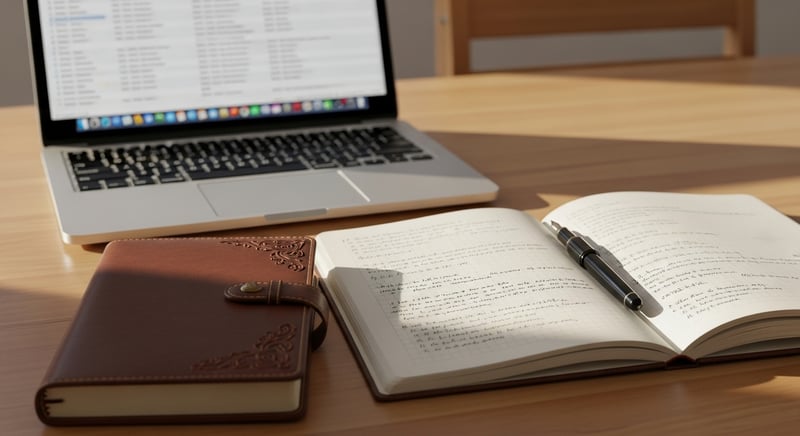
生成: ImageFX
#2:ビジネス現場での実践的な活用法
今井: 具体的に、私たちの業務ではどんな場面で活用できそうでしょうか?
村上: コンテンツ制作を例にとってみましょう。従来は「効果的なプロンプトを一度書いて、生成AIに一括で作業を依頼」していました。でもこうした対話型アプローチでは「生成AIとの継続的な対話を通じて品質を向上」させていく感じです。お気に入りの生成AIを育てていくイメージですね。
そして重要なのが、その対話プロセスの中で普段とは違う視点に立つことができることです。生成AIの回答を通じて、自分のバイアスや思考の偏りに気づくことができます。これは一人では実践できず、人間同士でも相手を選びますので、生成AIを使う大きなメリットになりますね。
いきなり記事の執筆を生成AIに依頼するのではなく、まず自分の仕事内容や、メディアの目的や方針などを共有していきながら、急がば回れで進めていくという感じですね。
高山: プレゼン資料の作成でも使えそうね!「明日、経営陣に向けて新商品の提案をします。どんな点を重視すべきでしょうか?」という相談から始めて、「この数字の見せ方、もっとインパクトのある表現はありませんか?」と段階的に詰めていく。
今井: それは良いアイデアですね~。生成AIを単純な作業ツールではなく、思考パートナーとして使うということですね。
村上: そうです!問題解決でも同様で、「この課題を多角的に分析してください」「従来とは違うアプローチはありませんか?」「この解決策のリスクはどこにありますか?」って、生成AIと一緒に考えていく感覚です。
高山: でも、これまでのプロンプト技術って意味なかったということでしょうか?
村上: いえ、そうではありません。「プロンプトは大事だけど、大事じゃない」という矛盾するような話になってしまいますが、これが現実だと思います。
今井: それはどういう意味でしょうか?
村上: 最初はプロンプト集を見たりして、効率的な指示を知ることは確かに大事です。でも、本当に質の高いものを作ろうとすると、プロンプトだけでは限界があるということです。そして「プロンプトを使いこなす=生成AIを使いこなす」ではないんです。
.jpg?width=800&height=436&name=Image_fx%20(2).jpg)
生成: ImageFX
#3:人間にしかできない価値と格差の拡大
高山: なるほど。プロンプト技術はあくまで入り口で、その先にもっと重要なことがあるということですね。
村上: まさにそう!本当に価値のあるコンテンツを生み出すには、人間が持つ独自の要素が不可欠なんです。
今井: 具体的には、どんな要素でしょうか?
村上: まず「経験に基づく洞察」ですね。実際に業界で働いた体験や失敗談も含めた一次データは、生成AIには真似できません。次に「文脈理解能力」。相手の立場や状況を考慮した判断も人間ならではです。
高山: 生成AIを使いこなすテクニックより、その人が持っている知識や経験の方が重要ということですね。
村上: そうです。同じテクニックを使っても、使用者によって結果は全く違うのが生成AIです。表面的にプロンプト集をコピー&ペーストするだけでは、一般的な情報の組み合わせに留まってしまいます。
今井: 一方で、専門知識を背景とした具体的な指示ができれば、業界特有の課題や文脈を踏まえた、より価値の高いコンテンツが作れると。
村上: 実は、これからの時代は格差が広がっていくと思うんです。プロンプトだけを仕入れて何とかしようという人と、そもそも能力が高くて様々な知識や物事の進め方を知っている人との差が、より顕著になるでしょう。
高山: つまり、生成AIを本当に使いこなすためには、自分自身のスキルアップが欠かせないということですね。
今井: 小手先のテクニックだけに頼るのではなく、人間としての基礎力を高めていきたいですね。

生成: ImageFX
#4:実践のステップと新時代のコンテンツマーケティング
高山:対話型アプローチをコンテンツマーケティングの現場で使っていくとしたら、どうしたらいいでしょう?
村上: 実際に始めるとしたら、3つのステップを提案したいと思います。
まず「生成AIとの関係性を構築する」。毎日少しずつでも対話を重ねて、一方的な指示ではなく相談や議論を心がけることです。 長く同じチャットで対話を続けることで、毎回ゼロから説明することもなくなり、自分の部下や同僚のように気兼ねなく相談できる相手に近づいていきます。
高山: 2つ目は?
村上: 「自分の専門性を明確にする」です。自分が最も詳しい分野や経験を整理して、その知識を生成AIと共有できる形で言語化する。具体的な事例やエピソードを準備しておいたり、抽象化・メソッド化して伝えやすく整理しておくとよいでしょう。
今井: 3つ目はなんでしょう?
村上: 「様々な視点で捉えてみる」ですね。生成AIとの対話では、自分自身の考えと異なるものも出てきます。そうした他者の視点を取り入れて、仕事の品質を高めていきましょう。マーケティング施策やコンテンツ成果についての専門的な視点や、ビジネス成果についての上司の視点、コンテンツの読者の視点…など様々な視点を積極的に取り入れていくことがポイントですね。
高山: ただ、注意すべき点もありますよね。情報の信頼性とか。
村上: はい。AIが生成する情報は必ずしも正確ではありません。特に専門的な内容については、複数の情報源との照合を必ず行う必要があります。生成AIの学習データには時期的な限界もありますし。
今井: コンテンツマーケティングの観点から見ると、この変化はどう捉えるべきでしょうか?
村上: コンテンツの質がより重要になってくると思います。表面的な情報の組み合わせではなく、作り手の経験や洞察が込められたコンテンツでないと、読者の心に響かないでしょう。
高山: 確かに、生成AIを使ったコンテンツ企画制作がもっと広まれば、誰でも一定レベルのコンテンツを作れるようになります。その中で差別化を図るには、人間らしい温かみや深みが必要ですね。
今井: 読者との信頼関係を築くという意味でも、作り手の人間性や価値観が伝わるコンテンツが求められそうです。
村上: まさにその通りです。九段理江さんに示していただいたような、生成AIとの関係性を深め、継続的な対話を通じて品質を高めていくアプローチに改めて注目していきたいですね。重要なのはプロンプト集ではなく、その人が持つ知識と経験、そして生成AIとの向き合い方だと思います。
まとめ
今回は、生成AIとの新しい向き合い方について話し合いました。
見えてきたのは、効率化追求だけではない生成AIとの付き合い方です。対話からはじまり、最終的には人間の創造性や専門性とAIの処理能力を組み合わせた「創造的パートナーシップ」へ。技術の進歩と共に、人間らしさの価値がより際立つ時代になりそうです。まずは小さな対話から、生成AIとの新しい関係を築いてみませんか?
執筆・編集:Content Marketing Academy
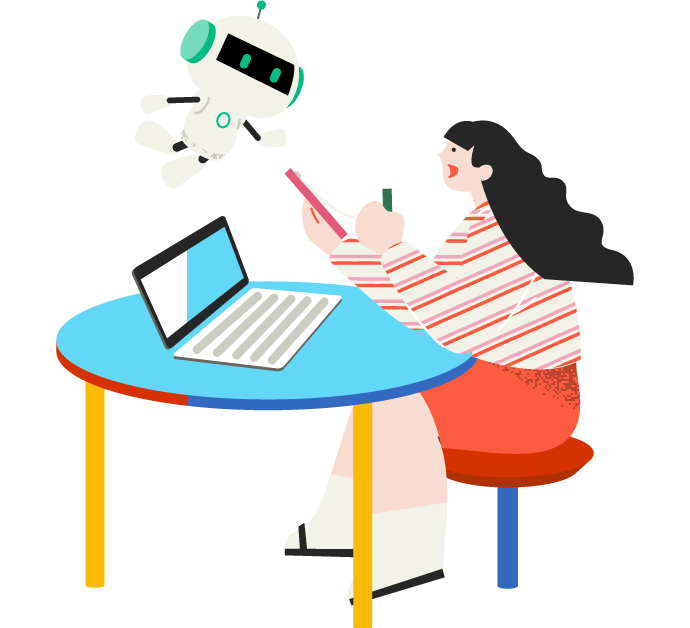
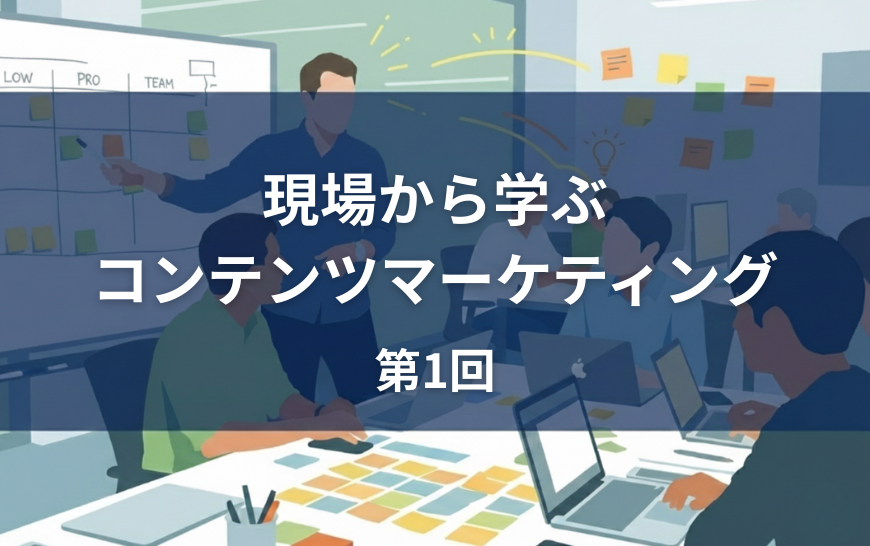
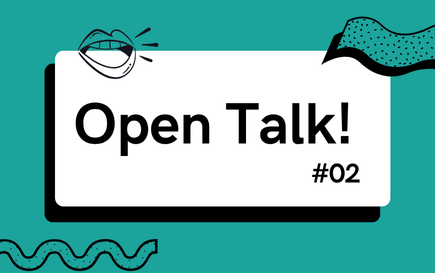
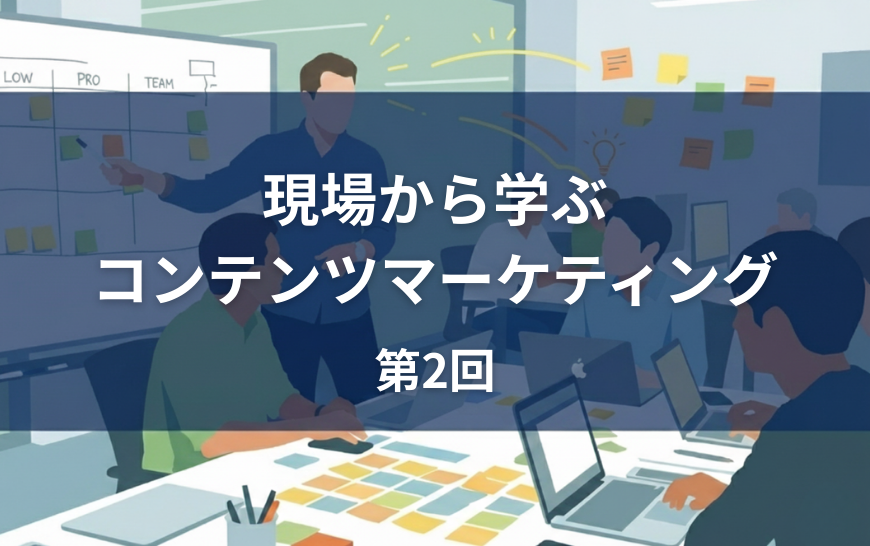

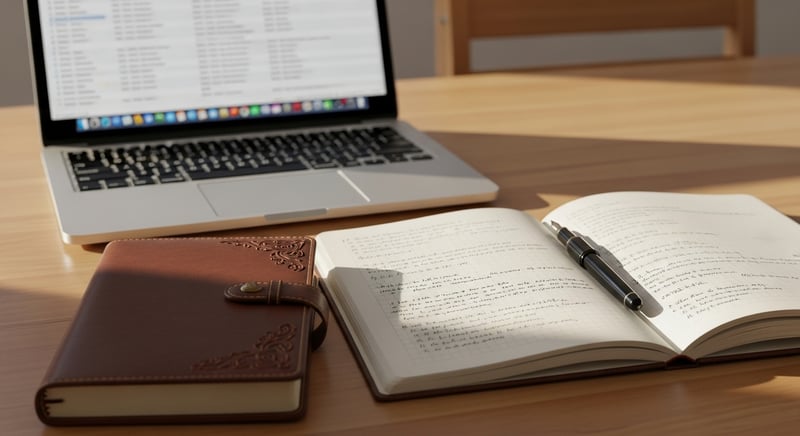
.jpg?width=800&height=436&name=Image_fx%20(2).jpg)