CONTENT MARKETING DAY 2024 レポート 第3弾:アドビ流「公式」コンテンツの届け方—信頼と発見を生む情報設計とは?
最終更新日: 2025.07.29

アドビ株式会社の加納宏徳氏と松谷昌俊氏が「CONTENT MARKETING DAY 2024」に登壇。企業が“公式”としてどのように情報を発信すべきかについて、自らの実践をもとに具体的な取り組みを紹介しました。少人数体制の中でどのように制作プロセスを構築し、ユーザーからの信頼を得る情報設計を実現しているのか──その裏側が語られるとともに、「届け方」の工夫を通じて公式コンテンツの価値をどう高めていくかが多角的に共有されました。
情報があふれる現代において、企業の「公式コンテンツ」には、正確性だけでなく、“どのように信頼を得るか”という視点が求められています。コンテンツは必ずしも最後まで読まれるとは限らず、検索やSNSなどで一部だけ切り取られて届くケースも珍しくありません。こうした現実をふまえると、企業が信頼を得るためには「届け方」まで含めた工夫が欠かせません。本セッションでは、アドビがどのように公式コンテンツを構築し、どのように届けているのか、実際の取り組みをもとに紹介されました。
登壇者のプロフィール
|
加納宏徳氏
アドビ株式会社にて、SEOスペシャリストとしてAdobe Expressのグロースチームに所属。松谷と共に、検索データを起点に、記事から動画にイベントまで、幅広くコンテンツマーケティングに取り組む。
学校からドロップアウトし10年間独学で英語やWEBを学ぶ。その後伝統工芸品の海外通販プロジェクト立ち上げ、外国人向け不動産スタートアップ、海外Webマーケティング代理店の部長職を経て現職アドビへ。趣味は世界中から応募がある大会で、グランプリを受賞した折り紙。個人で折り紙アートのプロジェクトを立ち上げている。 松谷昌俊 アドビ株式会社にて、SEOスペシャリストとしてAdobe Creative Cloud, Adobe Document Cloudの集客施策に従事。加納と共に、検索データを起点に、記事から動画にイベントまで、幅広くコンテンツマーケティングに取り組む。
業界内でも職人気質が強いことで有名な代理店にて、SEOコンサルタントとして数年経験を積む。コンテンツ設計から分析までを多く手がける。 マーケティング業界に入る前は、アメリカの大学院にてMBAを取得。大学院を含めてアメリカに約4年半の滞在歴があるため、英語を駆使しての仕事に興味があり、現職に至る。 |
1. 「誰が言うか」が重視される時代における“公式”の意味

生成AIやUGC(ユーザー生成コンテンツ)の普及により、私たちの周囲には日々膨大な情報が溢れています。とりわけIT・クリエイティブ業界においては、製品のアップデートが毎月のように行われており、ユーザーも発信者も情報のキャッチアップに苦労しているのが現実です。このような時代だからこそ、「誰がその情報を発信しているのか」が、信頼性を判断するうえで重要な基準になっています。
本セッションでは、加納氏が「どこかの通りすがりの人が薦めるより、製品の開発元である私たちが語るからこそ意味がある」と語られていたように、公式の立場から誠実に情報を届けることの重要性が改めて示されました。公式コンテンツは単なる“正しい情報”の提供ではなく、ユーザーにとって「安心できる」「試してみたい」と思える“納得感”を生み出すものであるべきなのです。
アドビでは、検索上位を目指すSEO的な観点にとどまらず、生成AIが参照するに足るようなコンテンツを意識して制作を進めています。具体的には、情報の正確性・構成のわかりやすさ・多様なプラットフォームに対応した見せ方といった点を重視し、どこからでも信頼してアクセスできる“素材”としての公式情報づくりに取り組まれています。
このように、「公式として出す」だけでなく、「公式としてどう伝えるか」までを設計する姿勢が、これからの企業コンテンツにおいて重要な視点であることが示されました。
2. 少人数でも回る、整合性ある制作フローの工夫
アドビのSEOコンテンツ運用は、加納氏と松谷氏の2名体制で行われています。限られた人数でありながらも、複数製品にわたる公式コンテンツを安定して制作・発信できている背景には、社内外との信頼関係と制作体制の工夫がありました。
特に注力されているのは、「公式として一貫性のある語り口」を社内外で共有することです。たとえば、外部パートナーと連携してコンテンツを制作する際にも、「アドビとしてどう伝えるか」という視点を共有することを重視されており、単なる制作指示ではなく、意図や背景を伝えながら進めているとのことでした。
社内との連携においては、部門を超えたコミュニケーションの場として「SEO Office Hour」という取り組みが紹介されました。これは、毎週1回、社内の誰でも気軽にSEOに関する相談ができる時間を設けたもので、営業やプロダクトチームとのやりとりを通じて、コンテンツの整合性や企画段階での方向性確認に役立てられています。
このように、少人数でも高い品質とスピードを両立するには、役割の分担や共通認識の徹底、そして社内外との信頼関係に基づいた柔軟な体制づくりが不可欠であることが示されていました。
3. 最後まで読まれない前提で、構造をどう設計するか

▲アドビでは、検索意図の理解だけでなく、途中から読まれても伝わる構成など、読み手視点でコンテンツが設計されています。
現代のユーザーは、膨大な情報の中から必要な情報だけを素早く取得しようとしています。したがって、コンテンツは最初から最後まで読まれるとは限らないという前提に立って設計する必要があります。
アドビでは、こうしたユーザーの行動特性を踏まえ、「長文の3分の2の箇所から読んでも要点がつかめる」構成を意識されています。段落ごとに内容が完結するように整理し、途中から読み始めても意味が通じるような工夫が施されています。これにより、検索やSNS経由で一部だけが切り取られて届いた場合でも、ユーザーが必要な情報を確実に受け取ることができます。
このように、構造・文脈・粒度の設計を丁寧に行い、ユーザーの意図に寄り添いながらも、どのような接点からでも正確に伝わる“読み飛ばされても価値が残る”コンテンツの設計が求められています。
4. ユーザーの“問い”に応えるための検索意図設計
ユーザーが検索する際の出発点は、「この製品を知りたい」ではなく、「こういうことをしたい」「この課題を解決したい」といった“問い”にあります。コンテンツを設計する際には、この検索の裏にあるユーザーの意図を的確に捉えることが重要です。
アドビでは、こうした検索意図を理解したうえで、ひとつのページの中に複数のニーズに対応できる構成を意識して制作されています。たとえば、Photoshopのユーザーであっても、画像の加工をしたい人、3D表現に挑戦したい人、あるいは背景を削除したい人など、目的はさまざまです。そこで、それぞれの“やりたいこと”に対応する段落や見出しを設けることで、読み手が自分に必要な情報にすばやくアクセスできる構造を設計しています。
また、検索エンジンにおける表示だけでなく、生成AIからの引用を視野に入れた設計も重視されています。AIに参照されやすいよう、情報が整理されていて構造が明確であること、そして信頼できる出典として機能することが、公式コンテンツに求められるようになっています。実際、検索結果やAIの回答欄に「このページから引用されました」と表示されるようなケースも想定し、コンテンツ全体がわかりやすく、意図が伝わるようなまとめ方を心がけているとのことでした。
こうした検索意図に即した設計は、ユーザーにとって「自分のための情報が見つかった」という納得感や体験価値につながります。単に製品情報を届けるのではなく、“問いに応える”姿勢が、使える公式コンテンツを支える柱となっていました。
5. 拡張する届け方:SNSと動画という「検索」チャネル
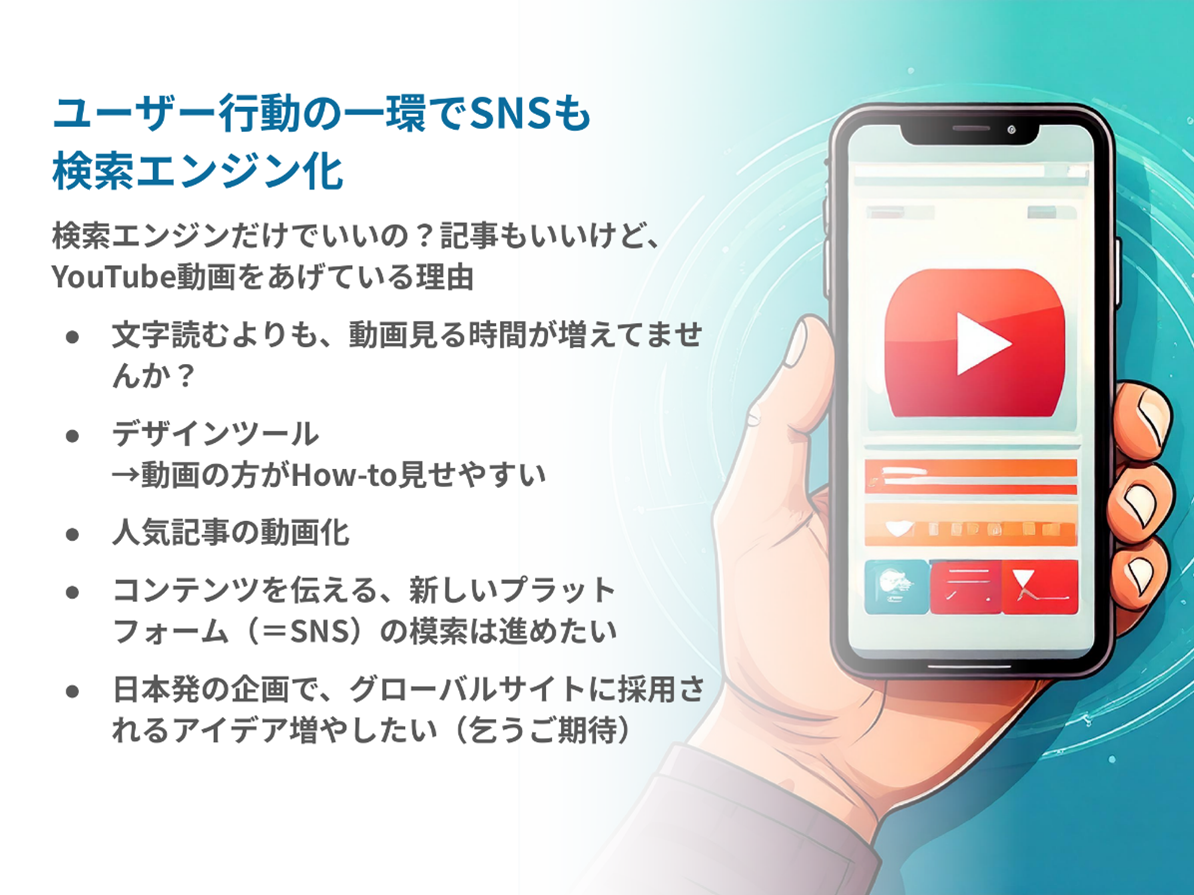
従来、情報探索といえばGoogleなどの検索エンジンが中心でした。しかし現在では、YouTube、TikTok、InstagramといったSNSや動画プラットフォームが、ユーザー行動の出発点となるケースが急増しています。SNSのタイムライン上で偶然見かけた動画から製品を知り、そこからGoogle検索や購入へと行動が展開する──こうした「SNS起点の検索行動」は、もはや例外ではなく一般的な流れになりつつあります。
こうした変化に対応するため、アドビでは記事コンテンツに加えて、YouTubeを活用した動画展開にも取り組んでいます。とくに人気記事のHow-toコンテンツを動画化し、操作の流れや機能の魅力を“視覚的・直感的”に伝える工夫が進められています。たとえば、「画像の反転」や「背景削除」といった機能は、文章で説明するよりも動画で見せた方が圧倒的に理解が早く、「なるほど」と一目で伝わります。「簡単です」といくら書いても伝わらないことも、5秒の動画で一目瞭然になる──そうした気づきが、動画活用を後押ししています。
また、届け方のスタイルも試行錯誤が重ねられています。編集を施した動画だけでなく、手元の操作をそのまま録画した“ラフな”動画の方がユーザーの反応が良かったケースもありました。さらに、サムネイルのA/Bテストを実施し、再生数や視聴維持率のデータをもとに改善を行うなど、動画コンテンツの最適化にも継続的に取り組まれています。
加えて、SNSや動画といったチャネルが検索の起点として機能する傾向が強まっていることをふまえ、検索エンジンだけでなくマルチチャネルを前提とした情報設計が重要になってきています。ユーザーがどのチャネルからアクセスしても情報が正確に伝わるように、表現や構成に工夫を凝らす必要があります。
このように、動画やSNSを「検索チャネル」として捉え直す視点は、これからの情報設計や届け方を考えるうえで欠かせないものとなっています。
こうした届け方の工夫もまた、ユーザーの視点に寄り添いながら公式コンテンツを設計するという、本セッションを通じて一貫して示されていた姿勢に基づいています。
まとめと感想
本セッションでは、企業が「公式」として情報を届ける意義と、その届け方に求められる柔軟性について、多角的な実践内容が紹介されました。構造設計、運用体制、チャネル選定といった各取り組みは、単なる制作ノウハウではなく、信頼性をどう構築し、ユーザーにどう伝えるかという視点に立脚しています。
以前のレポート(甲南女子大学・田坂氏のセッション)では、Z世代の学生が「公式らしさ」に対して距離を感じ、非公式な発信に親近感を持つ傾向が紹介されていました。一方でアドビの事例は、公式であることを前提としながら、それをむしろ強みに変える届け方を模索している点が特徴的です。2つの事例は一見対照的に見えますが、注目すべきはその表面的な違いではなく、いずれもユーザーの情報ニーズに正しく向き合おうとする姿勢です。ユーザーに合わせて届け方をどう設計するかが、学ぶべきポイントだと言えるでしょう。
企業の公式コンテンツにおいては、まず正確性や信頼性が前提とされますが、情報の受け手が多様なチャネルや文脈で接触する現在においては、それだけでは十分に伝わらない場面も増えています。検索やSNS、動画など多様な接点から情報が断片的に届く現代において、どこから触れても理解できる構造や、ユーザーの視点に合わせた伝え方の工夫がこれまで以上に求められています。
「公式だからこそ、どう伝えるか」。その可能性を改めて見つめ直すきっかけとなるセッションでした。
▼本セッションの内容に興味を持たれた方は、ぜひ実際の動画もご覧ください。
|

【CMD2024】コンテンツの届け方をデザインしよう!~ アドビで実践している、企業の「公式」コンテンツの作り方 ~【加納 宏徳氏・松谷 昌俊氏】
|
執筆:ウー・ピーター
CONTENT MARKETING ACADEMY リサーチャー
※本記事は執筆及び画像作成にあたり、ChatGPTを利用しています。
NEWS LETTERをお届けします!

コンテンツマーケティングラボの最新情報を、
定期的にEメールでまとめて、お知らせします
当月の更新情報を翌月初にお届けします。
(購読すると弊社の書籍発売イベントの特典資料をダウンロードできます)






