正しい物語を、正しい相手に語り続ける:セス・ゴーディンに学ぶAI時代のコンテンツマーケティング
最終更新日: 2025.10.16
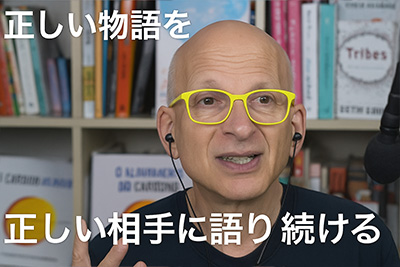
この記事でわかること
1. 物語を通じて価値を体現する
2. 戦術ではなく戦略を優先して整合性を持たせる
3. 誰に届けるかの選択が未来を決める
AIが情報を要約し、検索結果がリンクではなく生成されたテキストに置き換わる今、コンテンツマーケティングは大きな転換点にあります。ただ情報を発信するだけでは、ユーザーの目にも心にも届かなくなってきました。
そんな時代に改めて注目したいのが、「誰に」「どんな物語を」「どう語り続けるか」という本質的な問いです。
この問いを25年以上前から投げかけてきたのが、マーケティング思想家のセス・ゴーディンです。彼は著書「パーミッションマーケティング」で「ユーザーの許可を得たうえで行う継続的なコミュニケーションこそが、ブランドの信頼と選択を生む」と提唱しました。
例えば彼はこう言います。
“If you stop showing up, people complain, they ask where you went. That’s permission.”
あなたの発信が急に止まったとして、もし人々が「どこへ行ったの?」と不満を言ったとする。そこまでの関係性を構築できたならばそれは信頼関係の証だつまり、不特定多数に発信するのではなく、共感してくれる少数に語り続ける姿勢が、これからの時代には一層価値を持つということです。
本記事では、セス・ゴーディンのポッドキャスト出演(Better Marketing Pod Episode 42)での発言を中心に、「AI検索時代でも埋もれず、選ばれ続けるコンテンツとは何か」を4つの視点から紐解いていきます。
1) ストーリーテリングを中心に据える
マーケティングの中心にあるのは物語です。ゴーディン氏はこう語ります。
“Marketing is about how we’re going to tell a story that other people want to hear.”
マーケティングとは、人が聞きたくなる物語をどう語るかに尽きます。
例えば、洗濯機を「10kgの大容量」と説明するだけでは差別化は難しいでしょう。しかし「部活で泥だらけのユニフォームを毎日洗う家庭の安心ストーリー」として語れば、単なる数値ではなく具体的な生活のイメージとして響きます。
人が価値を判断するのは事実そのものではなく、その事実がどんな物語に組み込まれるかによるのです。
こうした物語は、AIが要約した事実やスペックの羅列では表現しきれません。今はAIが製品の特徴を瞬時に要約し、検索結果に並べる時代です。事実の羅列にとどまれば、すぐに比較対象のひとつに埋もれてしまいます。「この機能はどんな体験を生み出すのか」を言葉に変換することが欠かせません。
2) 戦術よりも戦略の整合性を
ゴーディン氏は、「マーケティングにおいて最も重要なのは、なぜその行動をするのかという戦略レベルの整合性だ」と繰り返し語っています。
広告の数値や話題性に一喜一憂するのではなく、「誰に」「どんな価値を届けるのか」というブランドの存在理由から逆算して、行動(戦術)を選ぶ必要があるというのです。
しかし現場では「動画がバズった」「TikTokで再生回数が◯万回」など、目に見える戦術的な成果ばかりが語られがちです。その背景には、大企業ほど分業が進み、担当者が目の前のKPIに最適化せざるを得ない構造があります。また、過去の成功体験が変化を拒む要因にもなります。
ゴーディン氏は、かつて話題になったスーパーボウルでのオレオのリアルタイムツイートについても、「あれは何も売らなかった」と喝破します。どれだけ多くの人に届いたとしても、ブランドの価値や顧客体験につながらなければ意味がないのです。
だからこそ、コンテンツを制作する前に「私たちはなぜ発信するのか?誰に向けて届けるのか?」という問いに立ち返ることが欠かせません。
この戦略レベルの整合性が定まれば、コンテンツは点ではなく線としてつながり、長期的なブランド体験として積み上がっていきます。AI検索によって一部のコンテンツだけが要約される今だからこそ、一貫性のある戦略が全体の印象を支える軸となるのです。
3) コンテンツそのものが価値である
ゴーディン氏によれば、ブランドとは約束(promise)です。顧客にどんな体験を提供するのか、その期待値こそがブランドの本質であり、その約束を最も強く伝えるのは広告ではなく、商品やコンテンツそのものです。外から飾り立てるよりも、体験そのものに価値を組み込み、自然に伝わっていく仕組みをつくることが重要なのです。
たとえばIKEAの無料カタログや組み立てマニュアルは、単なる販促物ではありません。顧客はカタログやマニュアルを通じて、商品を選ぶ楽しさや自分で組み立てる体験を先取りして味わうことができます。
記事や動画、レポートは売り込み目的にとどまらず、体験の一部として設計されることが求められます。触れることで新しい発見があり、次の行動につながるコンテンツは、ユーザーにとって歓迎される体験となります。その積み重ねが信頼を育み、長期的な関係性を築いていくのです。
たとえ一部だけを切り取られても、そこに十分な価値が含まれていれば、ユーザーは自然に続きを知りたくなり、関わりを深めていきます。逆に、クリックしなければ意味がないようなコンテンツは、存在しても見向きされなくなるでしょう。
見てすぐ役立ち、触れてすぐ価値を感じられるコンテンツを継続的に届けることが、選ばれるコンテンツへとつながります。
4) 顧客を選ぶことは未来を選ぶこと
ゴーディン氏はこう語ります。
“When you pick your customers, you pick your future.”
どの顧客を選ぶかが、自分の未来を選ぶことになるのです。
例えば無印良品は、「シンプルで自然体な暮らし」に共感する人たちを顧客として選び取りました。その結果、商品開発から店舗デザイン、コンテンツ発信まで一貫してその価値観を体現しています。顧客を選ぶことは同時に、自らがどんな価値を大切にするかを決めることでもあるのです。
AIが情報を整理し、要約を返す時代には、なおさら誰に届けたいのかをはっきりさせることが求められます。広く浅く発信するのではなく、価値観を共有する相手に語り続けることで、コンテンツの方向性もより明確になっていきます。
感想とまとめ
AIがコンテンツを要約し、選び、生成する──そんな時代にあっても、セス・ゴーディンの言葉は変わらぬ本質を突いています。大切なのは、ただ物語を語ることではなく、「誰に」「どのように」語り続けるかを見極めることです。
検索結果にリンクが現れず、情報がAIに要約されて届けられる今、「誰の記憶に残るか」「誰に許可されて語るのか」が、かつて以上に意味を持つようになりました。
どんな相手を選び、どんな価値を約束するのか──その選択が、ブランドの未来そのものをかたちづくっていきます。
そして共感してくれる相手に向けて、ブレずに語り続ける物語こそが、AIに埋もれず、人の心に残り、選ばれ続けるコンテンツを育てていくのではないでしょうか。
執筆:ウー・ピーター
CONTENT MARKETING ACADEMY リサーチャー
※本記事は執筆及び画像作成にあたり、ChatGPTを利用しています。
NEWS LETTERをお届けします!

コンテンツマーケティングラボの最新情報を、
定期的にEメールでまとめて、お知らせします
当月の更新情報を翌月初にお届けします。
(購読すると弊社の書籍発売イベントの特典資料をダウンロードできます)





