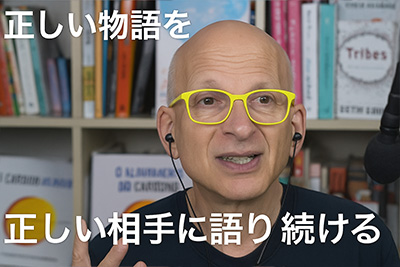AIで書いたらどう見られる?調査でわかった読者の本音
最終更新日: 2025.11.11

この記事でわかること
1. 読者はAIコンテンツをどう受け止めているか
2. 人間味を添えて価値を高める方法
3. Googleが評価する“中身重視”の基準
「AIで書いた文章は拒まれるのか?」
そんな疑問が聞こえてきますが、 調査が映し出す現実はもう少し複雑です。
読者は何を見て評価しているのか、その実像を追いながら、AIで書く意味を考えていきます。
1) 読者は「AIか人間か」を本当に気にしている?
AIで生成されたコンテンツについて、本当に重要なのは「誰が書いたか」ではありません。読者がAIコンテンツを受け入れる条件は、その情報が有益でわかりやすいかどうかにあります。
コンテンツ制作プラットフォームFoleonの記事("AI In Content Marketing: Do Consumers Still Care Who Writes It?")でも、この点が強調されています。
記事では次のように述べられています。
“Consumers aren’t fundamentally opposed to AI-generated content …
they want useful, relevant, and easily digestible information.”
消費者はAI生成コンテンツに対して強い抵抗を示すわけではなく、
役立ち、関連性があり、理解しやすい情報を求めているのです。
要するに、読者はAIそのものを問題視しているのではなく、有益でわかりやすい情報かどうかを基準にしているのです。
AIか人間かという出自の違いは本質的には重要ではなく、読者が求めているのは有益でわかりやすい情報なのです。
2) 「AIが書いた」と知らせたらどうなる?
読者がAIコンテンツを受け入れる条件は、「有益でわかりやすいこと」でした。
しかし、その前提を揺さぶる調査結果があります。
ヨーロッパの複数の大学による研究(“Users Favor LLM-Generated Content -- Until They Know It's AI”では、 次のような興味深い傾向が示されました。
AIだと知らされない場合、AI生成の文章は人間が書いたものより好まれることがあります。
しかし「これはAIが書いた」と告げた瞬間、評価が下がります。
つまり読者はAIコンテンツそのものを拒んでいるわけではありません。
「AIが書いた」と伝えられることで生じる心理的な影響――これが評価を左右しているのです。
有益でわかりやすい内容であれば、実際にはAIが関わっていても自然に受け入れられます。
しかし「AIです」と強調した途端、「本当に信頼していいのか」という疑念が頭をもたげます。
読者の判断を決めるのは誰が書いたかではなく、どう伝えられるかにあります。
こうした“告知の仕方”がもたらす微妙な心理の揺れを踏まえ、次はコンテンツに“人間味”を持たせるための工夫に目を向けます。
3) AIに“人間味”はどう足す?
AIコンテンツには「人間味に欠けるのでは」と不安を抱く声も少なくありません。
では、その「有益でわかりやすい」という条件を満たすために私たちはどうAIを活用すべきなのでしょうか。
英国のデジタル・マーケティングエージェンシーClick Consultの記事(“How to use AI for content creation without losing the human touch”)では、「人間味」を失わないことの重要性が指摘されています。
“AI is a powerful tool, but the core of producing great content still comes from human insight.”
AIは強力なツールですが、良質なコンテンツを生み出すために本当に重要なのは、
やはり人間の洞察なのです。
同記事は、人間の洞察が欠けたコンテンツは既存情報の焼き直しにすぎず、独自の価値や意見がないため、読者にとっても検索エンジンにとっても評価されないと警告しています。Foleonが示した「有益でわかりやすい」という条件を実現するには、人間ならではの独自性や感情を織り交ぜることが欠かせません。
たとえば、事実を並べるだけでなく、自社の視点や解釈を加えること。
ブランドの声や共感を込めた表現を選ぶこと。
「新機能の紹介」の場合、単にスペックを列挙するのではなく、「この改善でお客様の作業時間が半分になりました」といった具体的な効果を伝える表現が効果的です。
こうした工夫は、人間が後から追記する場合もあれば、AIにあらかじめ指示を与えて生成させることも可能です。重要なのは、AIに任せきりにするのではなく、人間が意図を持って関与することで、人間味を感じられるコンテンツにできるという点です。
さらに、AIが生成した内容に、体験談や顧客の声といった人間らしい要素を添えれば、読者に安心感を与え、信頼につながるコンテンツになります。
4) GoogleはAIか人間かを評価に使う?
コンテンツの価値そのものを重視する視点は、プラットフォーム側の立場にも表れています。
Googleの公式ブログでは、検索エンジンはコンテンツがAIで作られたか人間で作られたかを評価基準にしていないと明言しています。
評価の対象となるのは、有益性、独自性、そして信頼性です。
つまりGoogleの視点から見ても、「誰が書いたか」ではなく「何が書かれているか」が決定的に重要であり、AIであっても、有益で信頼できる内容であれば正当に評価されるのです。
感想とまとめ
人は、文章がAIによって“書かれた”かどうかには案外こだわりません。
しかし「これはAIが書いた」と知らされた瞬間、評価が揺らぐ――そんな複雑な反応を示します。
ここで重要なのは、「AIで書いた」ことと「AIを利用した」ことは別物だという点です。
AIに丸投げして生成しただけの文章と、人が意図を持ってAIを道具として活用し、独自の視点や温かみを加えた文章とでは、読者に届く印象も、信頼感もまったく違います。
AIを使ってコンテンツを作ることは、いわば“カット野菜”を使うようなもの。少し手抜きに感じて罪悪感を覚えるかもしれませんが、味付けや盛り付けを工夫すれば、立派な料理として仕上がります。
AIは下ごしらえを効率化するための強力な道具であり、最後に必要なのはライターとしての視点や感性というひとさじです。
その一手間が、読者に届き、心に残る一皿へと仕上げてくれるのです。
執筆:ウー・ピーター
CONTENT MARKETING ACADEMY リサーチャー
※本記事は執筆及び画像作成にあたり、ChatGPTを利用しています。
NEWS LETTERをお届けします!

コンテンツマーケティングラボの最新情報を、
定期的にEメールでまとめて、お知らせします
当月の更新情報を翌月初にお届けします。
(購読すると弊社の書籍発売イベントの特典資料をダウンロードできます)