AI時代に読書の大切さを見直す、ちょっと変わったセッション──。
少し意外に思われるかもしれませんが、これは、コンテンツマーケティングの世界で注目されている「読者の気持ちに響くコンテンツの作り方」について、読書をうまく活用する方法を通してお話しした、とても参考になるセッションです。
みなさん、こんな悩みはありませんか?
・記事を量産しても読者の心に響かず、すぐに忘れられてしまう
・AIに頼りがちで、自分独自の視点や深い洞察が生み出せない
・プロライターに依頼してもありきたりなコンテンツしか出来上がらない
これらの課題を解決するヒントが、このセッション動画には詰まっています。
語り手はプラスドライブの原正彦さん。コンテンツマーケティング会社を経営する傍ら、ビジネス書を15冊執筆し、年間100冊以上の読書を続ける稀有な実践者です。
2024年にコンテンツマーケティング・グランプリを受賞した「ハッケン・テンプ」メディアの立ち上げから取材・記事作成・編集まで総合的に手がけ、「率直な意見など生々しいコンテンツを提供している点が際立っている」という評価を獲得。その背景にあるのが、まさに本から得た深い洞察力でした。
思考力と言語化力を鍛えるには本がぴったり
原さんが、AI時代にあえて読書を推奨する理由は明確です。
「AIは速いアウトプットが取り柄だが、誰がやっても速いので、早いだけでは他人との差が出なくなる」
一方で本は、著者の思想と編集者によって練られた情報。じっくり読んでゆっくり思考することが、深い洞察と独創的なアイデアを生むことにつながります。ビル・ゲイツやイーロン・マスク、ジェフ・ベゾスといった名だたる起業家も深い読書を好んでいるとのこと。
さらに重要なのは言語化力。AIを使いこなすプロンプトの精度を上げるためにも的確な指示を出す言語化力が必要で「その総合的な言語化力は、読書によって培われる」と原さんは言います。
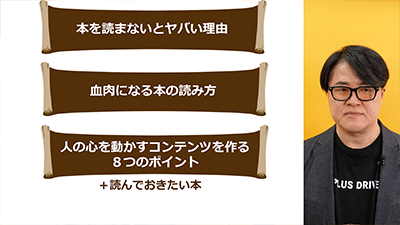
■コンテンツマーケティング担当者が学ぶべきポイント!
原さんが実践する読書法は、単なる知識習得を超えた戦略的なアプローチ。本から得た知識やノウハウを、実際の仕事で活用すると決めて読書しています。
そのため、移動中の隙間時間などを活用し、1日のスケジュールに「読書タスク」として組み込むことで、仕事と同じ優先度で継続。目的意識を持って読み進め、重要箇所は手書きでノートにまとめて記憶に定着させる──この徹底ぶりが、グランプリ受賞コンテンツの土台となっているのです。
収録中、特に原さんが力を込めてお話していたのは、こんなことでした。
「本は先人の知恵やノウハウが凝縮された効率の良いツール。目的意識を持って記憶に残りやすい方法で読んでいくべき」
人の心を動かすコンテンツを作る8つの実践ポイント
では、原さんは実際にどのような手法でグランプリ受賞コンテンツを作り上げたのでしょうか?
セッションでは「ハッケン・テンプ」で実践した8つの具体的なポイントと、それぞれを深く学べる推薦図書が詳しく紹介されています。メディアへの向き合い方から、ストーリー構築術、インタビュー技法、読み手目線の文章術、推敲のコツ、そしてSEOの本質まで──まさに「本から学んだ知識をコンテンツ制作にどう活かすか」の実例です。
「メディアメーカー」から「10年つかえるSEOの基本」まで、なぜこれらの本がグランプリ受賞に結びついたのか?その驚くべき活用術と具体的なノウハウは、ぜひセッション動画でご確認ください。
 ▲CMAの田所・村上と一緒に記念撮影
▲CMAの田所・村上と一緒に記念撮影
■ このセッションのポイント
AI時代にあえて読書を重視することで、差別化を図るためのヒントを学ぶことができます。
・AIに負けない深い思考力と言語化力を身につける読書術
・人の心を動かすコンテンツを作るための8つの実践技術
・グランプリ受賞コンテンツの制作秘話と具体的手法
ぜひCMD2025で、あなたのメディア運営を
次のレベルへと押し上げるヒントを掴んでください!
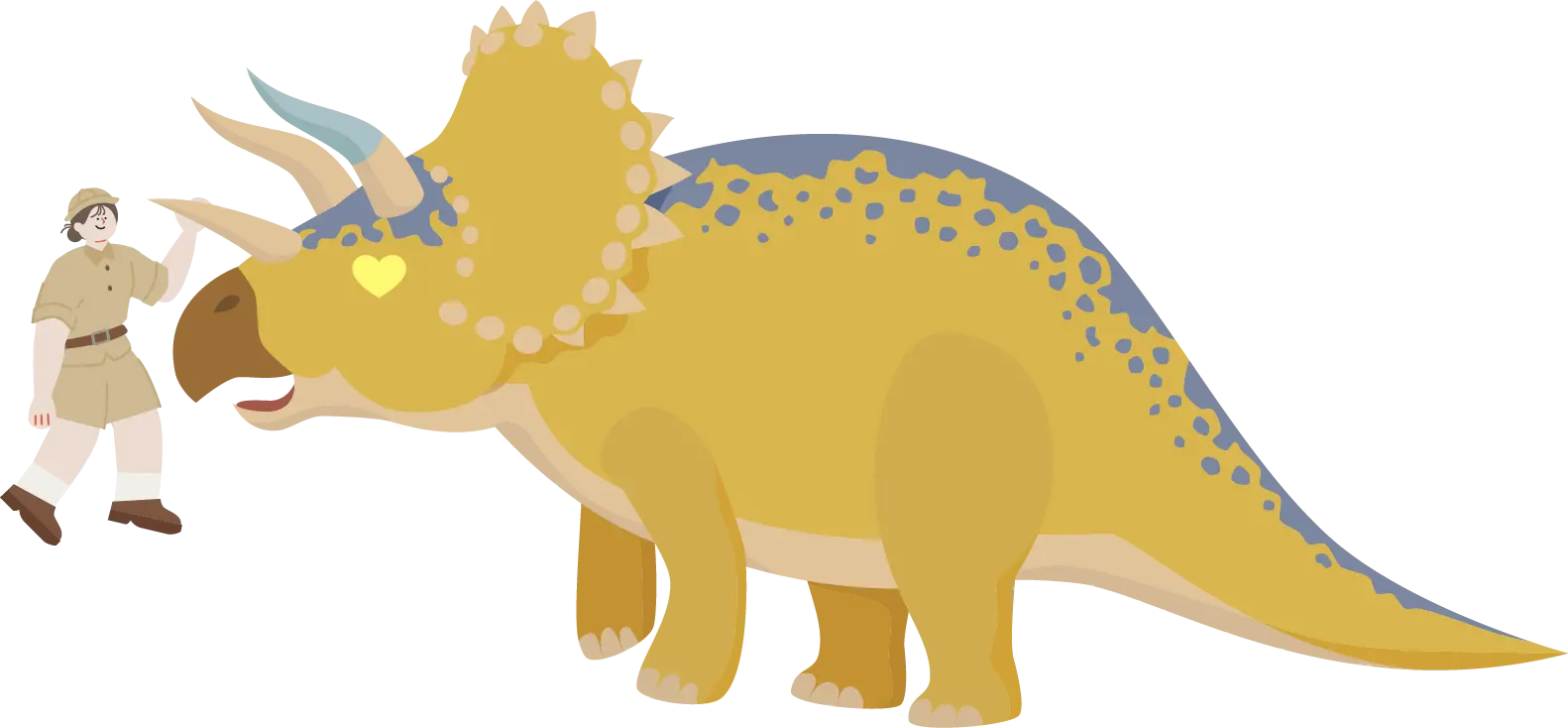




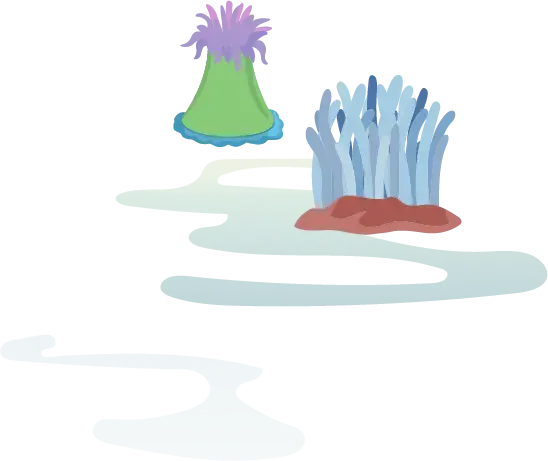










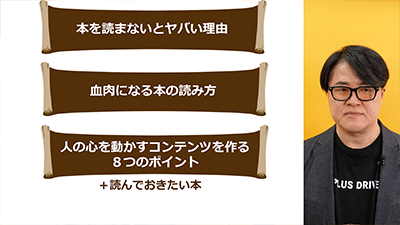

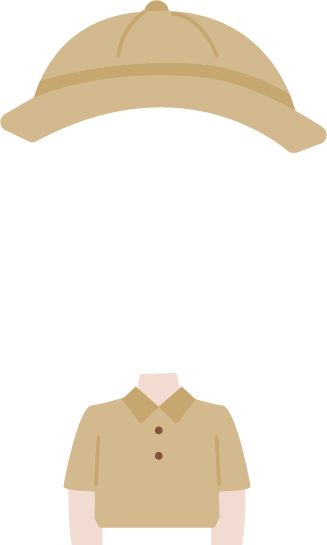


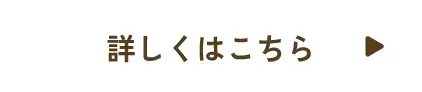

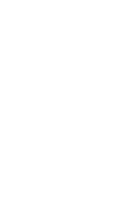

登壇者のコメント
今回の登壇を通じて、改めて「読書とコンテンツ制作の関係性」について深く考える機会をいただきました。AI全盛の時代に「本を読め」という逆張り的なメッセージをお伝えすることになりましたが、実際にクライアントワークの現場で感じるのは、インプット不足による企画力の低下です。
特に印象的なのは、検索やAIに頼りがちになった結果、深く考える習慣が失われていること。一方で、読書を継続している人材が手がけるコンテンツには、明らかに深みと独自性があります。
書籍は、著者と編集者というプロフェッショナルの手を経た高品質な情報源であり、そこから得られる構造化された知識は、AIでは代替できない価値を持っています。
ですから、これからも「人の心を動かすコンテンツ」を作り続けるために、“読書”という基本を大切にしていきたいと思います。本セッションを通じて、皆さんにも「“本の力”を活用したコンテンツ制作」の可能性を感じていただけたら嬉しいです。